広島特別支援学校を見学させていただきました!
先日、広島市立広島特別支援学校を見学させていただきました。
広島市立広島特別支援学校は、広島市で現状ただ1つの”市立”の特別支援学校で、小学部・中学部・高等部あわせて117学級・児童生徒総数577名(令和6年度)の学校です。
学校のホームページはこちら↓
https://cms.edu.city.hiroshima.jp/weblog/index.php?id=h1092

(これから入る!という場面に見えるよう後から撮影したものです。実際は寒い中教頭先生が出迎えてくださいました。ありがとうございました。)
校舎の内装
校舎の中は居心地良い素敵なデザインでした。とくに多数の大きな窓、天井から自然光が降り注ぐ「ひかりのひろば」といった、採光の工夫が印象的でした。
広い廊下、壁や階段には2段手すり、壁の角は丸くコルク素材、色によるエレベーターの区別等、安全とアクセシビリティへの配慮が感じられました。
こうした内装について、私達の引率者として共に見学した医師の先生は、「豪華な回復期リハ病棟のようだ」とおっしゃっていました。
また、廊下につけられた窓からは、厨房での給食の調理の様子を見ることができるようになっていました。生徒たちの食育やキャリア教育につながるようにと考えられたデザインとのことでした。
校舎の内装・外装の一部は佐藤総合計画のWebサイト(https://www.axscom.jp/project/no03389/)からも見ることができます。
学校の説明

ランチスペースで、教頭先生から学校についてご説明いただきました。
特別支援学校特有の教育過程の話から、市立特別支援学校のスクールバスの実施状況といった具体的な話まで様々教えていただきました。
喫緊の課題として、児童生徒数が急速に増えているため、教室が足りなくなってきているということを伺いました。場合によっては、やむをえず1つの教室をパーテーションで区切って2クラスが使う、ということもあるそうです。
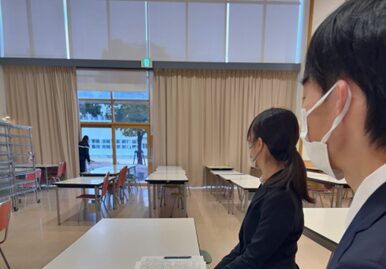
教室が足りないために、現在高等部の学生はプレハブで授業を受けているそうでした。
もうすぐ新校舎ができる予定とのことでしたが、新校舎ができたらこのプレハブは撤去(維持費がかかるため)となるため、教室不足が改善とはいかないようです。
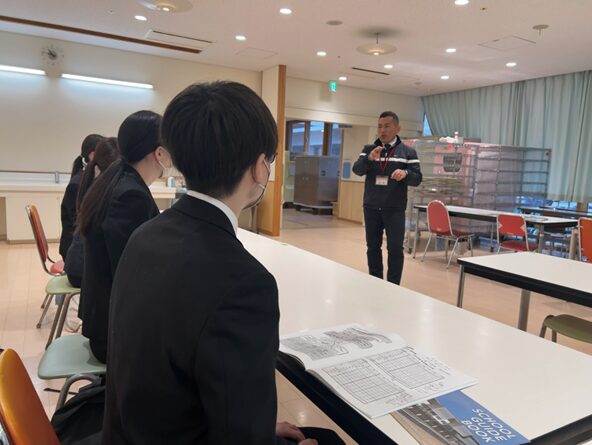
疑問に思ったことをたくさん質問させてもらいました。特別支援学校のカリキュラムについての疑問のほか、学校現場で先生方が実感されていること、役所や教育委員会との関係性についても、教頭先生は全て快く答えてくださいました。
校内・授業の見学
お話を聴いた後は、校内を見学させていただきました。
機能訓練室・言語指導室といった自立支援のための教室や、陶芸室・クリーニング実習室・接客販売実習室といった職業訓練のための教室が特徴的でした。
校内にはサポートセンターがあり、そこでは広島市立の幼稚園・小・中・高等学校の幼児児童生徒本人や保護者の方、学校関係者の方に対して教育相談を行っているそうでした。特別支援学校の教職員の先生がお子さんのアセスメントを行い、本人にあった過ごし方を一緒に考えていくと教えていただきました。
見学中、廊下で掃除をしている生徒の方たちに出会うことがありました。事前に教頭先生からお話は聞いていましたが、特別支援学校では「自立活動」「生活単元学習」「作業学習」が授業として行われており、掃除の活動もそのひとつとのことでした。
別のところでは、教室内で丸めた新聞紙をゴミに見立てて掃除の練習をしている児童も見かけ、このようにして段階的に学習していくのだなあと感じました。
見学を通じて

今回の見学を通じて、児童生徒の方々が十分な支援を受け、のびのびと学び、より良い未来を切り開くための力を養うことができる環境が整えられていることを実感しました。
この度見ることができた環境づくりの工夫や学習活動・支援を忘れないようにし、今後の私達の活動にも活かしていきたいと思います。
一方で、在籍児童生徒の急激な増加に伴う教室の不足や、特別支援教育の経験が豊富な先生の手が足りなくなってきているといった課題を抱えてもいると分かりました。
支援を必要とするお子さんが急増していることや、教員が不足してきているということは知っているつもりでいましたが、実際に見学に行ってみてその深刻さを感じることとなりました。
現場を見学をしてはじめて感じ取れたことが多くありました。
教頭先生をはじめ、学校の皆様、貴重な機会をいただきまして大変ありがとうございました!
